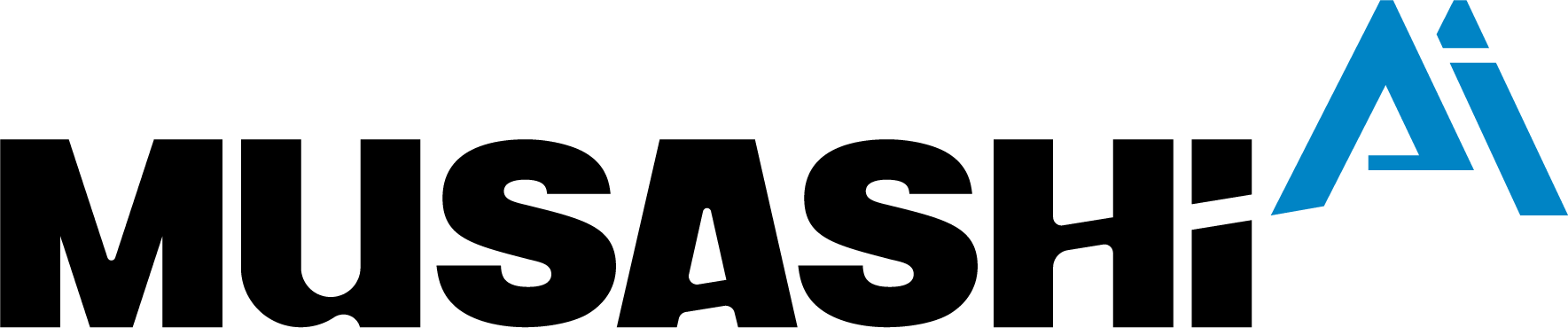エッジ端末を製造現場に導入する際の課題

近年注目されているエッジ端末ですが、製造現場に導入するにあたってどのような課題があるのでしょうか。
エッジ端末とは
エッジ端末とは、クラウドから遠い場所のエッジ(端)、より現場の近くにある端末のことです。現場の製造ラインから得られた情報をクラウドや社内サーバで処理を行うことなく、エッジ(現場)で処理を行うことができるため、遅延もなくネットワーク負担もないため、近年では導入が進んでいます。
エッジAIは文字通り、AIに必要な計算処理をクラウドにあげることなく、現場のエッジ端末で行うことを指します。
具体的にはスマートフォンやスマートスピーカー、車、カメラなどのIoTデバイスを指しますが、製造現場ではGPUなどの演算装置を組み込んだボックスを導入するケースが一般的です。
但し、理論上はメリットが大きくても、現実に動いている生産ラインにエッジAIを導入するためにはいろいろな課題があります。本稿では、どのような課題があるか、具体的に説明していきたいと思います。
エッジ端末を製造現場に導入する際の課題
製造現場へエッジ端末を導入するためには以下のような課題を解決する必要があります。
- DC24V電源への対応
- 制御盤への取り付け
- 熱耐性
- メンテナンス
- 停電リスク
DC24V電源への対応
製造現場で使用する制御盤内のデバイスは、AC200Vから変換したDC24Vを使用する場合が一般的です。そこに他の電圧レベル(DC19VやAC100V)のデバイスを実装する場合には、そのデバイスのためだけに電源を用意する必要があります。制御盤内のスペースは限られており、わざわざ1つのデバイスのためだけに電源を準備するのは効率が悪いため、デバイス側でDC24V電源に対応する必要があります。
制御盤への取り付け
制御盤へデバイスを取り付ける場合、基本的には、DINレールと呼ばれる専用の器具を使用します。DINレールに対応することで、他のデバイスと同様取り付けることができるようになり、スペースを有効に使用することができるようになります。
熱耐性/メンテナンス
制御盤内は夏場は暑く、冬場は寒くなります。極端に高温もしくは低温になる場合には、熱変換機や盤クーラーを使用して温度を調節しますが、デバイスは、通常摂氏0 - 45度程度の環境において連続して安定的に稼働する必要があります。デバイスの温度を下げる方法として、放熱フィンのみを使用したファンレス機構とファンにより空冷を行う機構とがあります。ファンによる空冷の場合、デバイスを冷却するにはとても有効ですが、メカ部品のファンが故障してしまうリスクがあります。そのため、交換のために生産ラインを長時間停止しておくわけにはいかないため、万が一、ファンが故障しても直ぐに交換できるようなメンテナンス性の良さは非常に重要になります。
停電リスク
製造現場では、終業時にデバイスがシャットダウンされる前に主電源を落とされることや、工場内の電圧低下による、瞬間停電(瞬停)等があります。このような状況の場合にも、故障することなく電源復帰後に通常通り機能するデバイスが要求されます。
エッジ端末を製造現場に導入する際の課題まとめ
本記事ではエッジ端末を製造現場に導入する際の課題についてまとめてみました。
弊社AI外観検査装置では、製造現場のニーズや現場に導入する際の課題を十分に考慮して設計されたエッジデバイスを採用しています。
ご興味がある方は、お気軽にお問合せください。